ご無沙汰しています。アーツシです。
本日は、皆さまに転職を前向きに考えていただくための小話をひとつ。
本編の前に
本編に入る前に、誤解のないようにお伝えしておきます。
本ブログにおいて「派遣エンジニア」という表現を使用する際には、一般的な派遣雇用形態としてのエンジニアのみならず、システム会社に正社員として雇用され、業務委託の形で客先に派遣されるSES(システムエンジニアリングサービス) のエンジニアも含めております。
私自身も過去に、正社員としてSESのエンジニアの勤務体系で3年間働いていた経験があります。
SESのエンジニアは、正真正銘の派遣社員よりは若干待遇の安定性が高いとはいえ、実態としては企業に派遣されて業務を行う形であることに変わりありませんでした。
客先常駐でないSES案件ももちろん一定数存在しますが、本メディアにおきましては、SESも含めた形で総称して「派遣エンジニア」という言葉を用いております。
この点をご理解いただいた上で、読み進めていただければ幸いです。
派遣エンジニアのボーナスシーズンは地獄
派遣エンジニアとして勤務していた当時、賞与は年に一度、年末の12月、クリスマスの日に支給されていました。
年の瀬に臨時収入があるというのは、本来であれば喜ばしい話です。
一年の締めくくりに少しだけ懐が暖かくなる――そんな風に捉える方も多いかもしれません。
しかし、派遣エンジニアとして働いていた私にとって、その実態は、
決して両手を挙げて喜べるようなイベントではありませんでした。
それ以前、私は映像制作会社で営業をしていたことがありました。
当時のボーナスは月給の3〜4ヶ月分が支給されており、まあ少なくとも「まとまったお金が入るイベント」ではありました。
それが自分の中の基準になっていたので、SESに転職した後も似たような感覚で構えていたのです。
初めて迎えた派遣エンジニアとしてのボーナス支給日。
通知を開いた瞬間、目に飛び込んできたのは「0.5ヶ月分」という数字でした。
0.5。なんとも繊細な数字です。これが大人の現実というものでしょうか。
軽い動悸がして、私は無言でトイレに向かい、15分ほど出てこられませんでした。
トイレの中で「自分の市場価値とは」「社会における私の役割とは」といった思索が渦巻き、
たぶん物理的に、壁に手をついていないと立っていられてなかった気がします。
その後も2年目、3年目と賞与は一応出ていました。平均して月給1ヶ月分程度。
とはいえ、元々のベースが高いわけではないので、手取りで20万円を超えたことは一度もありませんでした。
少ないこと自体は、もしかしたら人によっては割り切れるかもしれません。
しかし問題だったのは、その金額の根拠が何も明かされないという点です。
評価基準も、査定の指標も、まったく開示されません。あるのかどうかも分からない。
毎年、まるでブラックボックスに向かって「今年はどうか」と祈りを捧げる、そんな行事が行われていたように思います。
振り込みの連絡は、毎年だいたい11時過ぎ。
その時間になると、同僚の皆さん、そわそわとスマホやPCをチェックし始めます。
人間とは愚かなもので、「今年こそは違うのでは」と、根拠のない希望を抱いてしまうのです。
結果は、だいたい同じです。
無表情で席を立ち、静かに姿を眩ませる人。
笑いながら「いや〜今年もやられましたね」と言いつつ、目が笑っていない人。
何も言わずにモニターを見つめたまま動かなくなる人。
その日一日は、オフィス全体に妙な沈黙が漂います。
それぞれが「この感情をどこに向けたらいいのか分からない」という顔をしており、
明るい照明の下で、非常にシュールな地獄が展開されていました。
賞与額にキレ狂う先輩が教えてくれたこと
同じ派遣先で一緒に働いていた先輩が、2019年12月25日のクリスマス、隣の席で賞与明細が添付された会社からのメールを確認した瞬間、朴訥と、しかし圧倒的な怒りに身を震わせていました。
「これだけやって、こんなもんか…もう、何もしなくてもいいかなって、なりますよねぇ…笑」
その言葉と共に見せたのは、苦虫を7000匹は噛み潰したであろう、引き攣った笑顔でした。
この先輩ですが、当時30代後半にさしかかるくらいの年齢。
担当業務をこなすだけでなく、バッチファイルだのGASだのを駆使して、定常業務の自動化のフローを幾つも構築していました。
他のメンバーと比較しても仕事が大分に早く、客先においても折衝役も時折こなすなど、いわゆる「シゴデキ上司」と言っても決して過言ではなかったと思います。
この優秀だと思っていた先輩の受けた仕打ち、それに対する怒りを目の当たりにした刹那。
「構造的に、報われることのない仕組みの中にいるのかもしれない」という気づきを得ることができたのです。
私の前職に限らず、「派遣エンジニアは給料が低い、ボーナスも少ない」と嘆く声をよく耳にします。
しかし、それはある意味では当然のことです。
たとえるならば、まるで「沖に出ずに、大物を釣りたい」と言っているようなもの。
漁場によって釣れる魚が異なるように、エンジニアの働き方によって得られる報酬も変わるのは至極当然の話でしょう。
想像してみてください。沖に出て大物のマグロを釣る漁師と、岸辺で小魚を釣る漁師がいるとします。
- 沖に出る漁師は、大きなリスクを伴います。荒波に揉まれ、燃料費もかかるし、漁船や道具のメンテナンスも必要です。しかし、その見返りとして、高級マグロを釣り、高額な報酬を得ることができます。
- 岸辺で釣る漁師は、リスクも少なく気楽ですが、釣れるのは小魚ばかり。当然、それに見合った収入しか得られません。
仮に、沖に出る漁師がまだまだ駆け出しのそこそこの若造、岸辺で釣る漁師が老練なテクニックを有するやり手のベテラン漁師であったとしても、その結果は同じはずです。
人智を超越した奇跡が起きない限りは、時間がかかったとしても最初に巨大な高級マグロを釣り上げるのは沖に出たかけだし漁師の方でしょう。
派遣エンジニアは、いわば 「岸辺で釣りをする漁師」です
大物が釣れないのは、必ずしも貴方の能力が不足しているからという訳でもありません。
獲物にそもそもリーチできない場所にいては、貴方のスキルも宝の持ち腐れなのです。
言い換えれば、スキルがあっても、機会がなければその力は報われないということです。
先輩は、確かに腕は確かなエンジニアであったかもしれません。
ただし、当時の我々の立場にあって、「こんな収穫ではやってられない」と言うのは、あまりにも非合理的な考え方でしょう。
派遣エンジニアの給料が低いのは当然の話
派遣エンジニアの給与が低い理由は、単純にビジネスモデルの構造にあります。
- クライアント(派遣先企業)は派遣会社にお金を払う
企業は派遣エンジニアに直接給与を支払うわけではなく、派遣会社に対して報酬を支払います。
派遣会社は当然ながらビジネスとして利益を確保する必要があります。
企業から受け取る報酬の一部を自社の利益として確保し、残りを派遣エンジニアの給与として支払うのですから、中抜きをされた分、当たり前にエンジニアの取り分は少なくなります。 - 責任と報酬は比例する
上流工程(要件定義や設計)に関わるエンジニアは、企業の事業戦略に大きく関わる責任を担うため、それに見合った報酬が支払われます。
しかし、派遣エンジニアは決められた範囲の作業を遂行する立場であり、企業にとって「替えが効く」存在になりやすいです。
そのような派遣エンジニアは、あくまで外部の作業者であり、その業務のステークホルダーではないのです。
最低限の常識を有する委託先であれば、そんな派遣エンジニアに対して「責任を取ること」を期待して仕事を任せることはしません。
責任を求められるべき立場にないのですから、そこに報酬がのりにくいのもまた当然の話です。
責任と報酬は比例する
上流工程(要件定義や設計)に関わるエンジニアは、企業の事業戦略に大きく関わる責任を担うため、それに見合った報酬が支払われます。
しかし、派遣エンジニアは決められた範囲の作業を遂行する立場であり、企業にとって「替えが効く」存在になりやすいです。
そのような派遣エンジニアは、あくまで外部の作業者であり、その業務のステークホルダーではないのです。
最低限の常識を有する委託先であれば、そんな派遣エンジニアに対して「責任を取ること」を期待して仕事を任せることはしません。
責任を求められるべき立場にないのですから、そこに報酬がのりにくいのもまた当然の話です。
部外者、よそ者でいることで、大きな責任を負わず、比較的気楽に働ける側面はあるものの、その分得られる報酬も小さくなります。
沖に出ること
派遣エンジニアが「収入を上げたい」と思うなら、方法はただひとつ。
沖に出ることです。つまり、上流に行くこと。転職しましょう。副業を手に入れましょう。
- 中抜きされない仕事に転職する
上流の仕事をするエンジニアは、単なる作業員ではなく、企業のビジネスに貢献する存在として評価され安い傾向にあります。
要件定義、設計、プロジェクト管理といった上流工程に関わるスキルを身につける事で、プライムで案件をとっているSierに入り込むチャンス、あとは事業会社など発注する側に回ることも可能です。 - フリーランスになる
フリーランスとして高単価の案件を獲得することも、収入を上げる道の一つでしょう。
私は2、3年に一度、ちょっとした体の不調で不安に駆られ、自分が癌ではないかと恐れ、無為に苦しむような人間ですので、社会保険にしっかり守られる安心感を買うために正社員を続けているのですが、もし中抜きを究極に削ることを目指すのであれば、最終的には直取引できる立場を手に入れることが解決策だと思います。
本業として正社員しつつ、副業でフリーランサーとして企業と直接取引するような、ハイブリッドな働き方も推奨します。 - 市場価値の高いスキルを身につける
環境も重要ですが、それでもスキルもキャリアアップに不可欠であることに変わりはありません。
最新の技術(クラウド、AI活用、セキュリティなど)や、マネジメントスキルを身につけることで、より高単価な案件や職を獲得できるでしょう。
丸腰で海の藻屑とならないために
沖に出るというのは、単に「勇気があるかどうか」という話ではありません。
そこには、荒波もあれば、天候の急変もあります。
方角を誤れば、戻ることすら叶わないこともあるでしょう。
だからこそ、準備をせずに沖へ出ることは、無謀でしかないのです。
勢いだけで飛び出していっても、地図も羅針盤も持たないままでは、待っているのは”海の藻屑”という結末かもしれません。
転職市場という大海原も、まったく同じです。
求人票に書かれた文字だけを頼りに進もうとすれば、見えない地雷を踏むこともあります。
条件面や環境、成長機会、カルチャー、評価制度――それらの「本当の姿」は、外から見ただけではなかなか分かりません。
だからこそ、情報の非対称性を埋める存在として、転職エージェントは非常に重要な役割を担っています。
良いエージェントと繋がることで、
- 自分に合った職場を、事前に「内情」込みで知ることができる
- 想定年収や待遇に対して、現実的な「交渉」が可能になる
- 今のスキルで届く場所と、今後必要なスキルを明確にできる
- 案件選びの軸がブレず、迷いが減る
- 志望企業への「推薦文」が強くなり、書類通過率が格段に上がる
といった多くのメリットがあります。
一人で海に出るのではなく、経験豊富な案内人がついている航海と考えてみてください。
荒波に飲まれるリスクを減らし、進むべきルートを指し示し、必要であれば寄港先まで用意してくれる。
それが、信頼できる転職エージェントの存在です。
かくいう私も、複数のエージェントと話をすることで、ようやく自分にとって最適な航路を描くことができました。
最初から一本釣りで「この人だけに頼ろう」とせず、相性や対応、持っている案件の傾向を見比べながら、時間をかけて選びました。
情報武装をして、地図と羅針盤を手にした時、ようやく沖は「危険な場所」ではなく「可能性の広がる場所」へと変わります。
転職は人生の大きな航海です。
丸腰で臨む必要なんて、どこにもないのです。
今日はここで終わります
本日も長い間お付き合いいただき、ありがとうございました。
また近々お会いしましょう。
アーツシより ココロを込めて
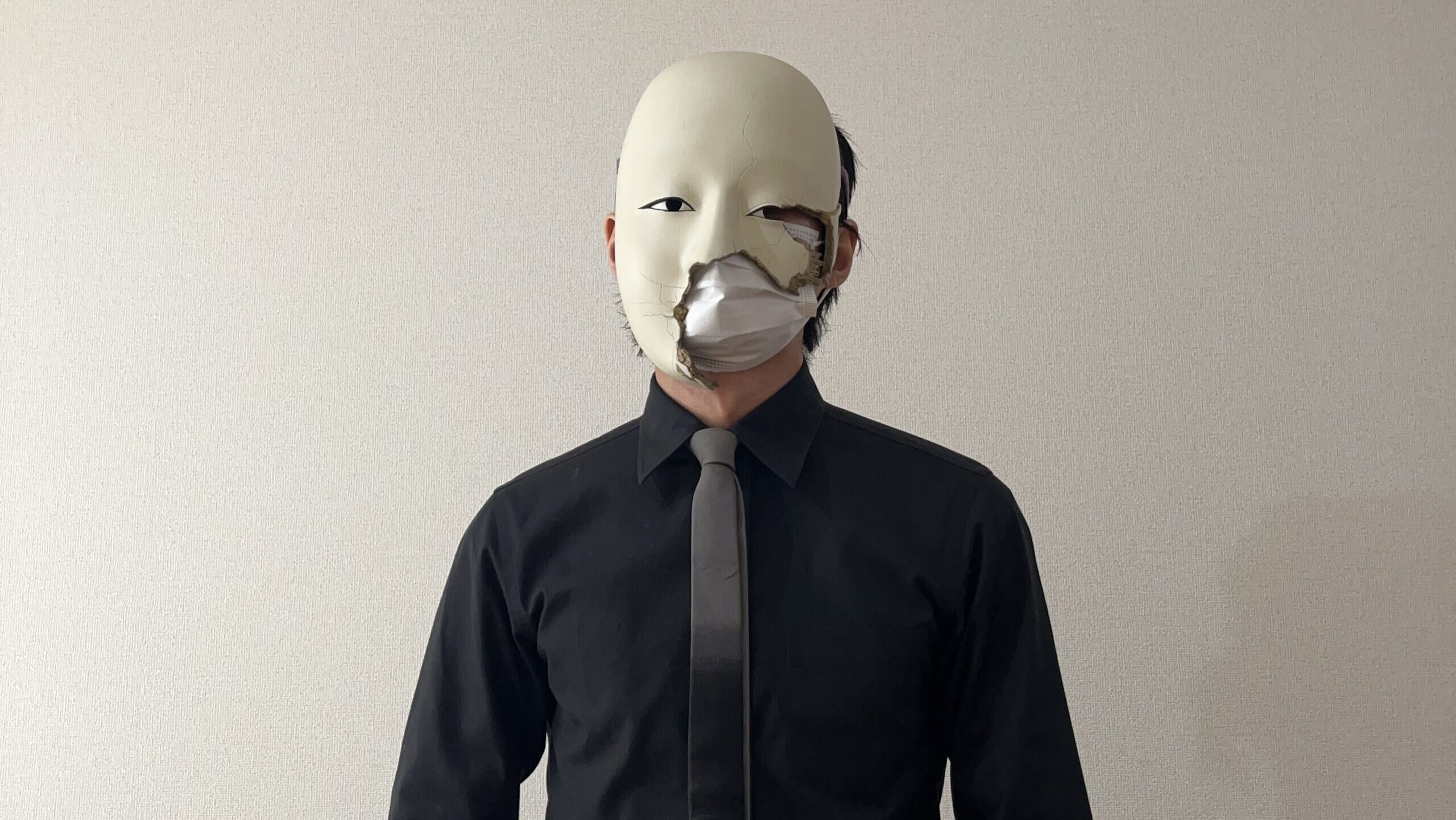


コメント